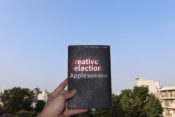【Creative Selection, Apple 創造を生む力//ケン・コシエンダ】(1.1/3)デモの重要性と、創作への転用
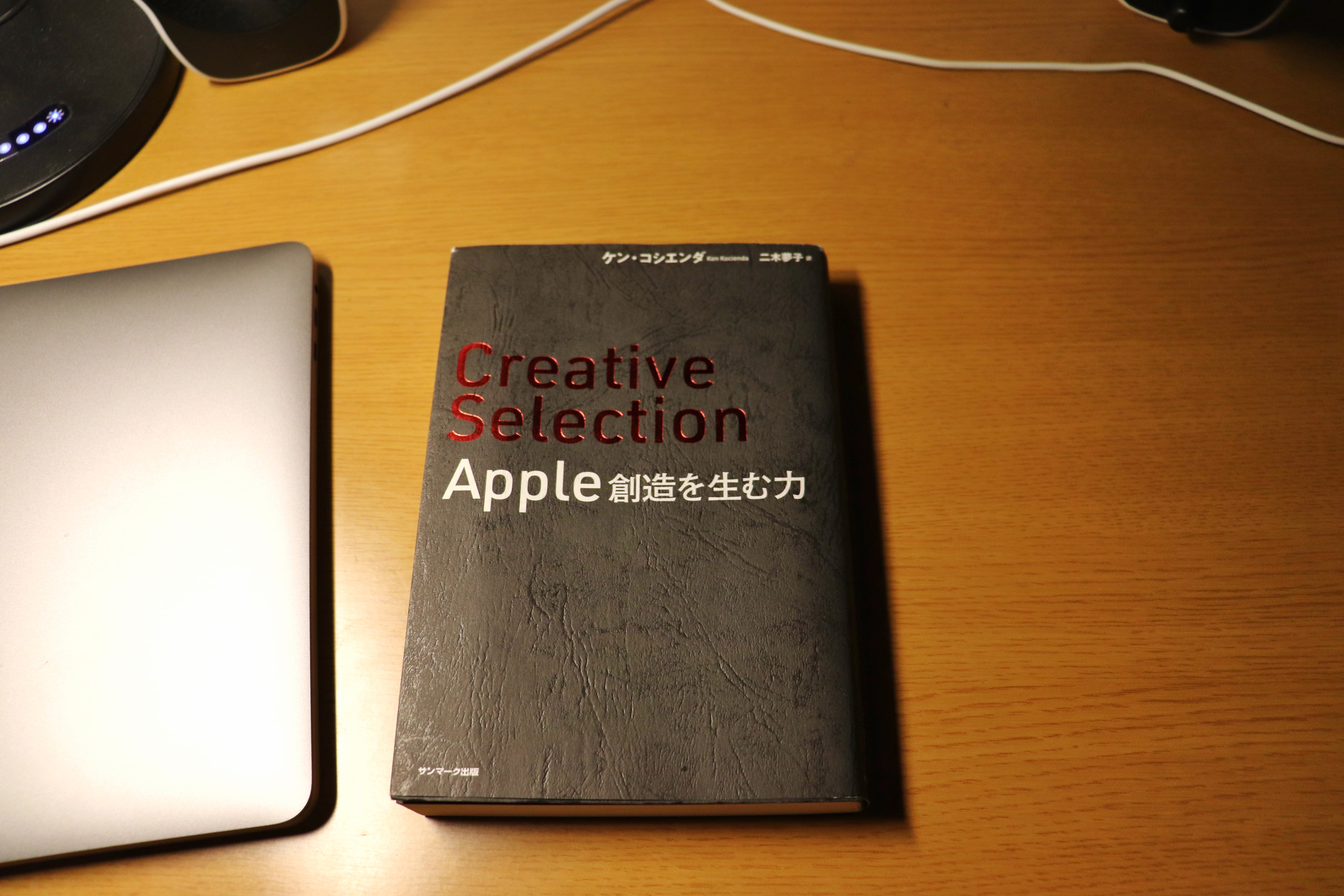
Contents
プロジェクトを適切に定義するためには
前回のあらすじと今回のイントロダクション
あらゆる創造的分野において、目指すべきは「最高のもの」である。
最高のものを作るにあたり、真っ白なノートでうんうん唸るやり方を否定する訳ではないが、その方法は時間の損失が大きい。では、有意義且つ確実且つ着実な進捗を実現するにはどうすればいいか。ちょうどエジソンが世界中の竹を試したように、試行錯誤あるのみである。99%の努力(≒試行錯誤)を積み重ね続けた人間だけが、最高のものを意図的に作ることができる。
しかし、試行錯誤とは言え、エジソンが竹以外の素材にも手を出していたら、最高のものに辿り着くまでにかかる時間と手間は天文学的な数字になる。あなたが死ぬ間際に「これだ!」という作品ができあがっても、それによって多少の印税等を稼ぐことができても、老後が少しだけ楽しくなるだけだ。できることなら、天文学的な時間ではなく、現実的な時間で「最高のもの」を作り、人生全体を楽しくしてほしい。
そのためには「プロジェクトを適切に定義する」必要がある。(ここでいうプロジェクトとは、あなたが成し遂げようとしている何か全般に該当する)
プロジェクトを適切に定義する=何かを成し遂げるプロセス全体を、適切な形で進行させる
そのために必要なことを、本書の紹介をしつつ、僕が考えたことを添える形で書いていこうと思う。
全ての思いつきに敬意を払う
「そうしたひらめきの爆発は全体から見ればあまり重要ではない」とエジソンが私たちに語っているかのようでもある
とはいえエジソンにとっては、有望なアイデアに基づいて、発明が実現するまでひたすら仕事を続けるほうが重要だったことは間違いない。
本題に入る前に、一つ言っておきたいことがある。
1%のひらめきと、99%の努力。
この言葉には、いささかの罠があるように思える。上の引用文になぞらえるなら、本当の意味で大事なのは努力の方であり、ひらめきの方は全体の1%にしか満たない、重要性は全体の100分の1だ、という解釈である。しかし、僕はこの解釈に異を唱えたい。ひらめきは重要じゃない、のではない。ひらめきはすごく重要だ。努力はその99倍重要だ。というニュアンスで解釈するべきだ。
(「ひらめき≒アイデアがまず浮かばないよ!」という方は是非こちらの記事をご参考ください)
ひらめきは重要、努力はその99倍重要。
そう思う理由はいくつかあるが、今回の記事の本旨に関して言うならば、エジソンが「有望なアイデアに基づいて」仕事をし続けた、という点がその最たるものだろう。エジソンは、有望なアイデア(ひらめき)に基づいてプロジェクトを定義したのだ。
しかし、厄介なことに、この「有望なアイデア」というのは、思いついた時点では、それが大規模なプロジェクト(≒成し遂げるまでに時間のかかるプロセス、時間をかけるに足る作業)に結びつくものなのか、あるいはそうでないかが分かりにくい。なぜなら、大抵の場合、とりとめもなく頭に浮かぶものは不格好であったり、洗練されていないものだからだ。中には「こんなの友人に伝えても怪訝な顔をされるだけだ」と思えるようなアイデアもある。そして、「こんなの考えるに値しない」と決め付け、頭の中の「忘れても良いリスト」に加えてしまう。これは良くない。アイデアが有望かそうじゃないかの判定は、極力するべきではない。もしかしたら、ひどく不格好で荒唐無稽で無関係に見えるアイデアが世界を変える大事業に発展するかもしれないからだ。
ジョセフ・プリーストリーは空気の研究の過程で、炭酸水を発明した。
パスカルは永久運動の実験中にルーレットを発明した。
もしも同僚が見たら「お前なんで炭酸水なんか作ってるんだよ」「ルーレットなんて永久機関でも何でもないじゃないか」と言うかもしれないが、その発明が今の世界をどれだけ変えたのかは、考えるまでもなく分かると思う。
だからこそ、あなたの頭に浮かんだ全ての思いつきに敬意を払って欲しい。
その思いつきを、直近で取り組むプロジェクトに組み込むべきか、あるいは手帳にでも書き残していずれ取り組むプロジェクトにするべきか、あるいは友人と飲んでるときに雑談やジョークのつもりで言うネタにするべきか、その判断は、次の段階にするべきだ。ただ、あなたの思いつき全てに敬意を払えば、その判断を正しく行うことができるはずだ。
前置きにしては長くなってしまったが、プロジェクトを適切に定義するための具体的な方法論を書く前に、これだけは言っておきたかった。
次から、具体的な方法論を紹介していこうと思う。
形のないビジョンを形にする
さて、この「1%のひらめき」は、他にインスピレーションやコンセプト、ビジョン、着想、初期衝動と言った言葉に置き換えられる。これらは全て、頭の中から不意に湧き上がるものである。それ自体に形はない。ふわっとしたもので、メモを残さなければ忘れてしまう可能性もある。だから、まずはこの「1%のひらめき」を目に見える形で具体的にしないといけない。「具体的に目に見えるもの」とは何か。それが、本書にてかなり重要なものとして書かれている「デモ」である。
デモとはつまり、その時点での暫定的な成果物と、それに付随するプレゼンテーションのことである。
このデモは、アップルの商品開発において、初期段階のビジョンを形にして示すだけに留まらず、プロジェクト(商品発売までのプロセス)の中で繰り返し制作されるものらしい。
なぜ、アップルがそこまでデモにこだわるのか。
デモを作ることのメリットを、書いていこうと思う。

うつくしい
デモの重要性
「具体例」を、目に見える形で共有できる
ここに「子犬の写真」が2枚ある。
次に、それぞれの選択肢のメリットについて話す。私は左側のゴールデンレトリーバーのかわいさについて主張できる。あなたは、愛らしいブルドッグのほうが好みで、犬らしい幸せな表情と、片方垂れた耳がさらにかわいさを増していると主張するかもしれない。私はまた反論して、ゴールデンレトリーバーの足が背の低い芝に埋まっている感じがとりわけかわいいと指摘するかもしれない。(中略)
ここで重要なのは、明確かつ具体的な例があるかないかが、「難しい、不可能とも思える議論」と、「子どもの遊びのような簡単な議論」の差だということだ。
ここで言う「子どもの遊びのような簡単な議論」が、引用文中の前半にあたる。
「ゴールデンレトリーバーの方がかわいい!」「ブルドッグのほうがかわいいもん!」
これは、子どもの遊びである。
反対に、「難しい、不可能とも思える議論(=どちらが可愛いかなんて主観的な問題だから容易には決着がつかない話し合い)」が引用文中の後半にあたる。なぜかわいいのか、どこがかわいいのかと言った具体例を示すことで、難しい、不可能とも思える議論にある程度光明が見えてくる。
デモを作るメリットは、まさにこの「具体例」にある。
頭の中にあるふわっとした「ひらめき」だけでは、そのプロジェクトの勘所がどこにあるのか、比較したり検討したりすることも難しい。
しかし、実際に形のある具体例としてデモを作っておけば、難しい、不可能とも思えるコンセプトもある程度具体性を帯びてくる。それによって、次にするべきプロセスや、どこらへんが要所になるのか、といったことも見えてくる。
具体例を目に見える形にすると、あいまいな議論に迷い込むこともなく、アイデアを洗練させやすくなるのだ。いわば、アイデアのデモンストレーションと言える。
そして、デモを次のデモにつなげる
アップルの仕事は、この基本的な事実に基づいている。
デモによって反応が生まれる。その反応は、きわめて重要だ。1回のデモに対する直接の意見が、次のデモに発展するための弾みになる。
明確且つ具体的なデモは、クリエイティブな決断を引き起こす触媒だ。
そして、クリエイティブな決断を早くすればするほど、それらの決断を洗練・改善する時間を多くとることも、必要に応じて後戻りすることも、可能なら先に進むこともできる。
あなたの頭の中に「これは」と思えるひらめきがあったとしよう。あなたはそれについて意見を聞きたい。そこであなたが喫茶店に友人を呼び出し、あれこれ話してみたとして、聞いている方は恐らく混乱するだろう。人の頭の中は思っているよりずっと非言語的で、それをリアルタイムで言語化しても系統だった説明など困難だ。それが、まだこの世に生を受ける前の熱量を持ったひらめきであるなら尚更だ。有意義なフィードバックなど望めない。
しかし、明確且つ具体的なデモを作りアイデアを具体的な形でデモンストレーションすることで、それを受け取る人間もひらめきがどんな形をしているのかハッキリ理解することができる。理解できれば、何が優れているか、反対に何が足りないかを具体的に指摘することができる。有意義なフィードバックが見込める。
そうしたら、そのフィードバックを次のデモに活かそう。
あとはもうその繰り返しである。
アイデアは徐々に洗練され、改善されていく。「最高のもの」に少しずつ近づいていく。
こういう作り方には、うんうん唸って飛躍的なアイデアを待つだけの時間や、聞き手が混乱するだけのミーティングもない。それによって浮いた時間は、「洗練・改善する時間」に割り当てたり、「必要に応じて後戻りすること」もできる。(やり直すのは簡単だ。一個前のデモを参考にすれば良い)そして可能なら先に進む。なんと合理的なプロセスだろう。
まとめると、
1%のひらめきを形にする(≒デモを作る)
↓
フィードバックを受けて、改善点を洗い出す
↓
試行錯誤(99%の努力)を経て、次なるデモを作る
↓
それを、完成に到るまで繰り返す
このプロセスにより、あなたの思いつき、1%のひらめき、初期衝動の類は具体的な形をとりながら少しずつ「最高のもの」に近付いていく。99%の努力とは、試行錯誤である。その試行錯誤が適切なものになるように(プロジェクトを適切に定義するために)、デモを作り、その進捗を具体的且つ着実なものにするのだ。
創作に転用する
僕は小説を書いている。
だから、ここでは小説に限って僕が考えたことを書こうと思うが、これを読んでいるあなたは、例によってあなたが成し遂げようとしている様々な分野にあてはめて適宜読み替えて欲しい。

下村敬、小説書いてる風
さて、僕の小説の作り方は、
①テーマ(伝えたいこと、書きたいシーン)が思い浮かぶ
↓
②それについて考えて、テーマを掘り下げたり、別の視点から眺めたりする
↓
③そのテーマを実現するためにはどういう展開が良いか、アイデアを出し続ける
↓
④それらを時系列順に並べて、プロットを作る
↓
⑤プロットを元に本文を執筆する
①は「1%のひらめき」にあたると思う。②の段階は、いわば「不格好であり、洗練されていない」テーマを少しでも実用的なものにしようとするプロセスである。そして、③が一番時間がかかる。④はもはや事務的な手続きであり、⑤は自分の知識と感性を元にプロットを装飾する作業である。(僕はプロットをかなりガチガチに書くので、「執筆」というより「清書」の方がニュアンスが近い)
こういう作り方をしているのだが、
今回本書を読んで、もう少し違う作り方をしてみようと思った所存である。
まず①と②。これは頭の中から抗いようもなく湧き上がるものだから、精々「どんな小さなテーマも紙に書き留めておく」くらいが関の山だ。
そして③。99%の努力。これに、前回の記事で書いた「試行錯誤」と今回の記事で書いた「デモ」を使ってみようと思う。つまり「こういうテーマがあって、このシーンはこういう意図を演出したいのだ」という目標をしっかり明記した上で、うんうん唸りながら「ベストな解」が頭に浮かぶのを待つのではなく、様々なシーン、文章を実際に書いてみた上で、それらを比較検討するのだ。(ここは必ずしも清書である必要はない、あくまで試行錯誤なのだから、ニュアンスさえ伝わる程度の文章で仕上げれば良い) そして、これだ、と思えた文章を「デモ」とする。
それを友人に読んでもらって、どう思うかを尋ねる。
もしも、未完成の、しかも一場面だけの小説を友人に読ませるのが恥ずかしいor申し訳ないorそういう友人がいないなら、しばらく保留にして次のシーンに取りかかる。創作とはその時点での熱量でどうしてもプラスの補正がかかりがちだ。次のシーンに取り組んで、ある程度時間をおいたら、今一度先ほどのデモを読み返せば良い。記憶が薄れる頃合いに読めば、書き上げた時には分からなかった粗が見つかるかもしれないし、あるいは反対に「ここって、結構いけてるじゃん」という発見もあるかもしれない。
試行錯誤。
シーンのデモの作成。
友人、あるいは自分へのプレゼン。
フィードバックを元にシーンのクオリティを上げる。
この繰り返しで、小説を作ってみようと思った僕であった。
この作り方は、きっと小説以外にも使える。是非、参考にして欲しいです。